アラフォー女性が主人公のファンタジー小説 [読書]

ファンタジー小説は読みつけないのでよく分からないが、40歳近くのヒロインが活躍する話って、なかなか珍しいのではないだろうか?
2巻のラストでは確か20歳くらいだった主人公のエリンも、3-4巻では一気に30代!ずいぶんと思い切ったな上橋さん!と驚いたのだが、折良くイヨンエ妊娠のニュースも報じられ、こういう感じで実写化したらアリかも、などと思ってしまった。
王獣の愛くるしさや、ファコの香りが漂ってきそうな料理の描写は相変わらず。ただし3-4巻ではお子様向けにはあまりふさわしくなさげな描写もあるか。エリン夫妻の熱々ぶり(朝チュンなど)には、気恥ずかしくなる部分も。
アンハッピーエンドの結末は4巻にさしかかる頃から予測していた。しかしあの残酷なラストについてはアマゾンの読者レビューでもいろいろな意見が出ており、そもそもこの続編は蛇足ではとの議論もあるようだ。
しかし、人間理性への絶対的な信頼という点から見れば、あながちアンハッピーではないかも、とも思える。民を愚かなままに保つ社会というのは、やっぱりいかんだろう。その点、著者に激しく同意するし、このラストを書かなかったらエリンの物語は終わらないのだ。闘蛇にはちゃんと足が生えていなければならない。
表紙の恥ずかしさには目をつぶる [読書]

当初はジュンク堂での立ち読みだけで済ませるつもりだったのだが、周りの目線に耐えられなくなり(気にしすぎなのだが)、ついに購入。いつもはエコの観点からブックカバー反対派の僕だが、今回ばかりは別だ。
有名(らしい)なビジネス書の理論を、弱小高校野球部の経営に取り入れたらどうなるか?という、いわば「はじめにネタありき」という感じのおもしろ本。たしかに、野球部の女子「マネージャー」って、名前のわりには「マネジメント」という言葉の持つエグゼクティブ感とはかなり開きがあるよな。
そもそも野球部なんて営利団体ではないのだから、ビジネス書を手本にしても仕方ないんじゃないか?と僕などは思ってしまったんだけど、それが素人の浅はかさ。『マネジメント』はあらゆる組織に適応可能な万能指南書であるらしい。
まずは、組織の定義付け(目的)をはっきりさせるところから始まり(野球部であれば、人々に感動を与えること。野球をすることが目的、という単純なものではない)、その組織の顧客は誰か?顧客が求めているものは何か?等々、ひとつひとつ丁寧に確認するように導かれる。
中には、組織が何を提供したいかではなく、顧客が何を求めているかを優先させないといけない、とか、専門家のアウトプットが顧客の(あるいは組織の)インプットに結びつかなければ意味がない、とか、なんだか大学の学生指導にも適用可能な箴言がぱらぱらとちりばめられていたりする。ちょっと、本家のドラッカーも読んでみるべきかな。
ストーリー展開はベタである。しかし、ライトノベル的な舞台設定の中で、いかにもビジネス書っぽい生硬な語り口が展開されると、思わぬ異化効果がありなかなかに面白い。1,2時間で読めてしまうので、未読の人はぜひ。あるいは著者は当世流行のAKBのプロデューサらしく、登場人物も当て書きらしいので、近々ドラマか映画になるのかもしれぬので、それを待つという手もある。
イタい先生の話 [読書]

正直、この作品を読むまで、田山花袋の『布団』のことは、読んでみようと思ったことさえなかった。花袋自身がモデルとなっている中年の文学者が、若い女弟子に横恋慕し、しかし案の定女弟子は恋人を作って去って行ってしまい、文学者は去った女弟子の残して行った布団に顔をうずめて泣く、という話だそうだ。なんともイタくて情けない話にしか聞こえないが、青空文庫でそのさわりをちらりと読んでみると、この中年文学者の設定が「35~6歳」となっており、なにやらどきっとする。
で、その現代版翻案とも言えるこの『Futon』は、花袋を研究するアメリカ人大学教授デイブを主人公にし、デイブが若い日系人の学生相手に『布団』を地でいくようなみっともない恋愛をしているという「イタい」ストーリーを軸にし、そこにデイブの執筆する『布団』のスピンオフ小説を挟み込みこみながら描いたもの。さらに、デイブの物語に加え、東京に住んでる女学生の曾祖父と、彼に関心を持つ若い画家イズミのストーリーも加わってくる。
感想としては、はじめデイブと、作中小説の中の時雄(つまり、『布団』の主人公)との痛さ加減が面白く、引き込まれて読むが、次第に比重を増していく女学生の曾祖父の、曖昧模糊とした記憶の世界についての描き方が、実に興味深く思えてきて、あっという間に読了してしまった。
記憶の構築性、「人の思い出話なんて当てにならないものだ」、っていうような話という点で、カズオ・イシグロの作品を連想するが、この『Futon』では、その思い出の曖昧さというか虚構性が、お年寄り(しかもほとんど「ボケて」いるような)の繰り出すのらくらした一人語りとして書かれているのが、なかなかにスリリング。
これだけ登場人物が多いにもかかわらず、どの人物の心理描写にも破綻した所がない(ように見える)。スピンオフ小説の部分だけとっても十分に読み応えある短編になりそう。感服。
僕たちの戦いは始まったばかり [読書]
 以前このブログで取り上げた、アラブ発のアメコミ風漫画「ザ・ナインティーナイン」だが、さきほど15号にて「第一部終了」となってしまった。
以前このブログで取り上げた、アラブ発のアメコミ風漫画「ザ・ナインティーナイン」だが、さきほど15号にて「第一部終了」となってしまった。さては不人気のジャンプ漫画よろしく、「僕たちの戦いは始まったばかり」とかいって連載中止になってしまったのかと気を揉んでいたが、最新の第16号では新メンバーが一挙に増えて、新展開を迎えているようだ。
左のキャラは、リビア出身のアイシャなる少女。「Samda th invulnerable」のパワーを持つとのこと。الصمدと言えば「永遠に続く」という神の美称だが、そこから「傷つかない、頑丈な」という意味合いに解釈しているのだろうか。鳩が飛んできても、モンスターが迫ってきても、彼女の周りには見えないバリアが張られて敵を寄せ付けない、という設定になっている。
この他、なんでもお見通しの「全知」少年のالعليم、体の各パーツを伸び縮みさせるالواسعが登場する。
第一部でもずいぶんといろんなパワーの持ち主が登場したが、僕のお気に入りはこれ。
 ミンダナオで慈善事業に携わるホープという名の女性で、司るパワーはالودود「愛を与える」だ。彼女がパワーを発揮すると、敵も味方も目がハートマークになってしまう。第15話では敵の総帥Raghulも彼女の力で戦意を喪失してしまっているので、今のところ最強のキャラではないだろうか。
ミンダナオで慈善事業に携わるホープという名の女性で、司るパワーはالودود「愛を与える」だ。彼女がパワーを発揮すると、敵も味方も目がハートマークになってしまう。第15話では敵の総帥Raghulも彼女の力で戦意を喪失してしまっているので、今のところ最強のキャラではないだろうか。不死身のパワーを得たという設定のRaghulにも、生身の体のまま死にそうになっている奥さんがいたりして、敵役の描写もなかなかに凝っている。第二部ではRaghulをどうやって再登場させるのか、まだまだ目が離せない展開である。
京都大学物語 [読書]
関西生活も早五ヶ月が過ぎようとしている。関西と言っても海辺の方なので、京都なんていう内陸の雅な所とには、なかなか足を踏み入れられずにいる。が、後学のためにこんなのを読んでみた。
 鴨川ホルモー
鴨川ホルモー
京大、京都産業大、立命館、龍谷大と、京都市内にキャンパスを構える4大学が登場するので、「京都キャンパスガイド」的な読み方ができるのがおもしろい。何大学のそばには何神社があって..、というのが、陰陽五行に基づく独特の世界観でもってマッピングされているのだ。京都の地理に元々詳しい人であればなお楽しめるのだろうが、僕のような初心者でも十分乗れた。
こういう妙な世界観は、『鹿男あおによし』でも見られたパターン。というか『鹿男』の方が新作なので、『ホルモー』の方がルーツなのか。
『鹿男』は先のテレビドラマ化の際に非常に惹かれるものがあったのだが、この手のドラマを毎回欠かさずチェックして鑑賞するという年齢でもなくなってきているせいか、1,2度見ただけで終わってしまっていた(武侠ドラマなら毎週録画してるくせに)。ところが最近になってこれも原作を読んで、玉木ンの「おれ」やはるかタンの「藤原君」ならじっくり見直してもいいかなと思い始めているところだったりする。DVDレンタルは始まってるんだろうか。
さて『ホルモー』だが、主人公を含め主な登場人物はみな京大生。こういう大衆的小説で、高学歴学生ばっかり出てくるのも珍しいんではなかろうか。
高学歴と言えば、漫画になってしまうが『東京大学物語』をついつい思い浮かべてしまう。そんなに熱心に読んだわけではないがあの作品だと、主人公たちの「東大」への思い入れはずいぶんと気合いが入っており、正直疲れるテンションの物語だったような気がする。まあ江川の作風のせいでもあるだろうけど。
ところが『ホルモー』の場合は、登場人物みなが京大生であることなんてほとんど気にすることなく読めてしまった。「イカキョー(いかにも京大生)」な高村なるキャラクターは出てくるが、その使い方も実に巧みでさりげない。なんというか、気負いや嫌みが感じられない。『東大物語』から10年くらい経っているだろうか。この間東大生、京大生というものに対する世間のとらえ方も、ずいぶんとソフトなものに変わってきた、ということか。
あと大学のサークルを舞台に、っていう設定がうまいなと思った。「京大青龍会」だとか「龍谷大フェニックス」だとか、いかにもありそうでなさそうなサークル名。名前だけ聞いたら、いったい何やってるサークルなんだか分からない感じ。そういうの、自分の学生時代にもあったなあ。小説の中では「イベントサークル」なんていう風に説明するシーンもあったし。そういう、大学のサークルのなんでもありな雰囲気と、京都の歴史の風合い漂う混沌とした感じ。うまい取り合わせだ。
なんだか夢中になって、続編の『ホルモー六景』まで読んでしまった。「丸の内サミット」の続きも気になる。東京で言うとどの辺の大学が出てくるんだろうか。あと「イカトー」って言う言葉はあるんだろうか。
 鴨川ホルモー
鴨川ホルモー京大、京都産業大、立命館、龍谷大と、京都市内にキャンパスを構える4大学が登場するので、「京都キャンパスガイド」的な読み方ができるのがおもしろい。何大学のそばには何神社があって..、というのが、陰陽五行に基づく独特の世界観でもってマッピングされているのだ。京都の地理に元々詳しい人であればなお楽しめるのだろうが、僕のような初心者でも十分乗れた。
こういう妙な世界観は、『鹿男あおによし』でも見られたパターン。というか『鹿男』の方が新作なので、『ホルモー』の方がルーツなのか。
『鹿男』は先のテレビドラマ化の際に非常に惹かれるものがあったのだが、この手のドラマを毎回欠かさずチェックして鑑賞するという年齢でもなくなってきているせいか、1,2度見ただけで終わってしまっていた(武侠ドラマなら毎週録画してるくせに)。ところが最近になってこれも原作を読んで、玉木ンの「おれ」やはるかタンの「藤原君」ならじっくり見直してもいいかなと思い始めているところだったりする。DVDレンタルは始まってるんだろうか。
さて『ホルモー』だが、主人公を含め主な登場人物はみな京大生。こういう大衆的小説で、高学歴学生ばっかり出てくるのも珍しいんではなかろうか。
高学歴と言えば、漫画になってしまうが『東京大学物語』をついつい思い浮かべてしまう。そんなに熱心に読んだわけではないがあの作品だと、主人公たちの「東大」への思い入れはずいぶんと気合いが入っており、正直疲れるテンションの物語だったような気がする。まあ江川の作風のせいでもあるだろうけど。
ところが『ホルモー』の場合は、登場人物みなが京大生であることなんてほとんど気にすることなく読めてしまった。「イカキョー(いかにも京大生)」な高村なるキャラクターは出てくるが、その使い方も実に巧みでさりげない。なんというか、気負いや嫌みが感じられない。『東大物語』から10年くらい経っているだろうか。この間東大生、京大生というものに対する世間のとらえ方も、ずいぶんとソフトなものに変わってきた、ということか。
あと大学のサークルを舞台に、っていう設定がうまいなと思った。「京大青龍会」だとか「龍谷大フェニックス」だとか、いかにもありそうでなさそうなサークル名。名前だけ聞いたら、いったい何やってるサークルなんだか分からない感じ。そういうの、自分の学生時代にもあったなあ。小説の中では「イベントサークル」なんていう風に説明するシーンもあったし。そういう、大学のサークルのなんでもありな雰囲気と、京都の歴史の風合い漂う混沌とした感じ。うまい取り合わせだ。
なんだか夢中になって、続編の『ホルモー六景』まで読んでしまった。「丸の内サミット」の続きも気になる。東京で言うとどの辺の大学が出てくるんだろうか。あと「イカトー」って言う言葉はあるんだろうか。
失われた写本の謎 [読書]
 輝く日の宮
輝く日の宮 『源氏物語』には失われた一巻があった!というお話。新聞で紹介されていて興味を持った。
丸谷氏の文章は、実を言うと新聞で見かける論説の他には読んだことがなかった。旧仮名遣いについて行けるか不安はあったが、読んでいくうちに、「さうだらうと思つた」などと言うような文体も気にならなくなり、あっという間に読めてしまった。
旧かな以上に気になったのは、「あたし」という一人称。女子中学生から四十代の大学助教授(女性)まで、みな「あたし」である。空想の中の紫式部にまで「あたし」と言わせているのにはびっくりしたが、博学な丸谷氏のこと、ひょっとすると「あたし」という表現にも何か言語学的に正しいという裏付けがあるのかもと思ってしまった。
で、「あたし」を使うからと言うわけでもないが、女性の描き方なんかはうすっぺらい。いかにも中年男性好みの女性像という感じがする。まあ薄っぺらいと言えば男性もそうだったか。それはともかく。
あと、主人公が国文学研究者という設定になっていて、研究会で大御所をこてんぱんに批判したら本が出版できなくなってしまったり、シンポジウムで彼女に嫉妬する他の研究者から品のない嫌みを言われたりとか、学界の裏話的なエピソードがちりばめられている。しかしこれらのエピソードも何となく物足りなく感じてしまうのは、最近まで一連の「マックスヴェーバー論争」を読んでいたせいだろうか。事実は小説よりも何とやらだ。
で本題だが、実は僕は、「○○の失われた一冊の謎を追え」みたいな話は大好きである。源氏の散逸巻というのはどうやら丸谷氏の創作ではなく、実際に学問的な裏付けのある話だそうで、もうそれを聞くだけでわくわくしてしまう。しかし、残念ながら僕は源氏を読んだことがない。あさきゆめみしさえ読んでいないので、若菜の巻の文体がどうだこうだと言われても今ひとつ実感が湧かなくて、ちょっと残念である。そういう文体の違いが、主人公が散逸巻の謎を突き止める重大な根拠の一つとなっていただけに。
しかし、散逸巻の秘密が、作者である紫式部とパトロンにして編集者(にして愛人)である藤原道長の2人の間の営みにだけ帰せられてしまうと言う筋書きは、おもしろくもあり、不満でもあった。そもそも源氏という作品は、本当に紫式部の著作であると言えるのか?作品と作者の間に一対一の関係が取り結べるような類の作品だったのか?僕の好みとしてはやはり、藤原定家あたりがなんらかの意図から源氏の一巻を封印してしまった、みたいなオチが読みたかったかな、と思う。その場合の定家は、思いっきり邪悪で冷血な盲目の修道士みたいな造形で描いてほしい。
喧嘩上等な研究書 [読書]
 マックス・ヴェーバーの犯罪―『倫理』論文における資料操作の詐術と「知的誠実性」の崩壊 (MINERVA人文・社会科学叢書)
マックス・ヴェーバーの犯罪―『倫理』論文における資料操作の詐術と「知的誠実性」の崩壊 (MINERVA人文・社会科学叢書)2002年の初版以来、学界の注目を集めている書らしい。上記アマゾンでのカスタマーレビューの白熱度を見れば、この本の持つインパクトが伺える。著者の批判はマックス・ウェーバーに止まらず、ウェーバーに追随する日本の社会学者にも向けられており、日本のウェーバー学を牽引する折原浩氏は著者に対して猛反論を展開している。
タイトルからしてそうなんだけど、「あおるだけあおってやれ」と言う態度が文体からにじみ出ている。これだけ喧嘩上等な研究書っていうのも珍しいので、まあおもしろいと言えばおもしろいのだが、「情緒的」だとか「小児じみた」だとか「巨人」の肩に乗る「子供」だとか言って批判されている日本のウェーバー学者の側は、そりゃたまったもんじゃないだろう。記述は総じて饒舌、冗長。ウェーバーが付している長々しい「注」について批判する割には、自分の注がむっちゃ長い。本書に書かれた内容を普通に論証するだけならば、半分の分量で済むんじゃないかと思える。くだくだしく攻撃的な表現を多用し、2ちゃんの書き込みを彷彿とさせる。そのくせ「せざる得ぬのである」なんていう妙な言い回しが出てきたりする(「を」は?)。まあ、偉大な家父長ウェーバーを論駁するには、また「一読者」にすぎない著者が自分を弁護をするためには、これだけの回りくどさが必要だったということだろうか。
くどくて自分語り的な文体に目をつぶれば、というか、その文体自体を面白がって読むことに慣れてしまえば、本書の論旨は明快なのですんなりと飲み込めてしまう。古典的名著『プロ倫』で、ウェーバーがいかにいい加減な資料引用をしているか、いや、それは実はいい加減なのではなくて、都合の悪い事実を隠蔽しようとしているらしいのだが、ともかくウェーバーによる作為的な資料操作のあり方を細かく検証している。本書を読む限り、ウェーバーの資料操作に関する著者の指摘は的を射ているように思えるのだが、社会学の観点からするとどうなんだろうか。
正直言って、僕は今まで『プロ倫』なんてろくすっぽ読んだことない素人なのだが、本書で著者が『プロ倫』のエッセンスを紹介すればするほど、『プロ倫』の本質主義的な物言いが気になって仕方なくなってしまった。だって、プロテスタントの諸民族こそが資本主義の精神を生み出すのに適していた、っていう主張なんでしょう、つまるところ?それって、ちょんまげを結っていた日本民族はそもそも狩猟民族であり、したがって文明開化に乗り遅れずに済んだのだ、みたいな司馬遼太郎的主張と同レベルな、『プレジデント』流の文明論なんじゃないの?だから、本書の第四章で著者がまがまがしく『プロ倫』の根幹となる論証部分を論駁している下りを読んでも、「へー」という感想しか持たなかった。
あと、著者は「文献学」の手法を用いている、と言う風に語っているけど、これは自戒を込めて言っておきたいのだが、自説に都合のいいところだけを一生懸命になってソースをあたる、っていうのは本当の文献学ではない(はずだ)。文献学って言うのはもっとこう、ストイックで、一山全部掘り返してみてスプーン1杯分くらいの砂金が取れれば御の字、という感じではないか。初めっから金脈の位置が分かっていて、それをぐりーんと掘り進んでいってお宝ゲット、みたいなのはちがうと思うのだ。この本の著者は、それこそウェーバーの掘ろうとしていた金脈の位置はあらかじめ分かっていたのだから、どんなに外国語聖書の初版本にあたろうと、たいした労力ではない。学者として当然の作業だ。もちろん、その当然の作業をウェーバーが怠っていたと言う指摘は正しいのだが、まあ100年のタイムラグがある相手にそんなこと言ってもねえ。ともかく、こういうのを文献学と呼んでほしくない。むしろ、「ウェーバー学」と呼ぶのがふさわしい。
ともあれ、折原氏の反論書を注文したので、到着を待つことにしたい。今の自分にはちょっとデトックスが必要かも。
漫画の神様の脱神話化 [読書]
 テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ
テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へキャラとキャラクターの弁別、コマ構成やコマなんとかなどの用語法など、ちょっと読んだだけではすんなりと頭に入らなかった。それは僕が漫画の実践に携わっていない素人だからだろうか?
しかし本書の主旨は明快。「手塚は映画的手法を用いた」、「日本の漫画は映画的手法を取り入れて発展した」、したがって「日本の漫画は手塚によって発展させられた」。これって確かに何か間違ってるよねえ。本書はいわば、このような三段論法の矛盾を指摘し、漫画の神様手塚の脱神話化を行った。
著者によれば、映画的手法なるものは手塚が最初に導入したものではないし、そもそも映画的手法とは具体的にどのようなものなのかの検討は漫画批評において十分になされてはこなかった。その背景には、漫画というメディアがサブカルの代表格のように扱われてきたために、文学や映画の批評のようには、学問的検証に耐えうる批評がなされにくかったことがある。平易な漫画を小難しく語るな!といういちゃもんが常について回るわけだ。
だから、「手塚は日本の漫画の創始者」「手塚は偉いったら偉い」というテーゼがいったん共有されてしまうと、それを実証的に批判することも相当難しくなる。でも考えてみれば、手塚ひとりの作品を検討して日本の漫画史すべてを語るなんて、相当に乱暴なことのはず(夏目房之助の手塚論はおもしろかったけど)。本書の掲げる「手塚への円環を断ち切る」という目論見は、きわめて重要なことと理解する。
主旨は明快、なんだけど、論証の仕方が若干「くどい」ように感じる部分が多々あった。短文をなんども重ねて先行研究批判する下りなど、もちょっと淡泊に書いてくれた方が読みやすいのに、と思ったのだが、まあこれは文体の癖か。それとも漫画批評の方法論を確固たるものとして提示するのを急ぐあまり、アカデミックな文体の臭みが誇張されてしまったのかもしれない。
アメコミとポケモンの間らへん [読書]
 「イスラーム圏初のヒーローコミック『The 99』」(ソース:R25)という情報を知り合いに教わった。
「イスラーム圏初のヒーローコミック『The 99』」(ソース:R25)という情報を知り合いに教わった。で、さっそくデジタル版を買ってみた(我ながら早ッ)。
まず最初の巻の前書きで作者が面白いことを書いている。
われわれの主人公たちは、スーパーマンやバットマンみたいな、西洋的なindividual heroesでもなければ、東洋のポケモン型の、チームワークや共有する価値観ですべてを乗り越えていくのでもない。彼らは東洋と西洋との混合体だ。
なるほど、アメコミとジャパニメーションの双方の良いところを取ったアラブ版というところか。
で、まだ初めの数冊しか読んでいないが、いやー、これは面白い。アッバース朝が滅ぶときに、「知恵の館」、ダール・アル=ヒクマの叡智の粋を結集して作った99個の「ヌール・ストーン」が、フレグの征西の際に持ち出され、なんやかんやあってちりぢりになり、現代になりそれぞれの玉の能力を持つヒーローが登場する、というプロローグ。史実に題材を取った壮大なファンタジーを予感させる。 99の玉の能力というのは、ご存じイスラームの神の99の属性に対応していて、「制圧者(ジャッバール、الجبار)」「光(ヌール、النور)」「害を与える物(ダーッル、الضارّ)」なんていうキャラが次々と出てくる。99という数が多いという意見もあるが、水滸伝の108人に比べれば9人少ない。 で、上のR25の記事には「登場するヒーローは..イスラム教徒の男女」とあるが、これは間違いで、どう見てもイスラム教徒ではなさそうなアメリカ人やらポルトガル人やらも能力の持ち主として登場するようだ。要は、「神の美名」というのは単なる方便で、ファンタジーを成り立たしめるベースではあるものの、物語全体が宗教ベースというわけでは全然ない、というのが僕の感想だ。 似た例を挙げるならば、『ジョジョの奇妙な冒険』第三部の「スタンド」。あれは確かそれぞれのキャラがタロットカードの絵柄に相当するスタンド能力を持っている、と言う設定だった。ちょうどそんな感じで「神の美名」が使われているのだ。そう言えば絵柄も何だか似てる気がするし、ひょっとしたら作者は『ジョジョ』を読んでる?とさえ思えてきた。いや、『ジョジョ』もアメコミを意識して描いているだろうから絵柄が似ていても不思議はないのだが。いずれにせよ、何でもかんでもイスラームで説明しようとしてはいかん。 序盤ではまずサウジの少年が「ジャッバール」の力に目覚め、次にアラ首連のシャルジャの女子大生が「ヌール」の力に目覚める。その二人が本作全体の道化回しとも言えるドクター・ラムズィーの引き合わせで出会い、それからアメリカの「ダーッル」の持ち主を探しに行く、という展開。公式サイトの人物紹介を見ると、これからロンドンやらインドネシアなど舞台が広がっていくものと思われる。「地球の運命」と言いながらアメリカのことだけしか描かないハリウッド的世界観に比べれば、何ともワールドワイドだ。 そんなわけで今、この漫画のこの後の展開が気になって仕方がない。『The 99』が乗り越えるべき課題としては、こんなものがあるだろう。 第一に、敵の設定をどうするか。今のところ、中世のアラブ人科学者(マッド・サイエンティスト?)の化身であるラグルという人物が悪役らしいのだが、彼は何を象徴するのか?アメリカとか資本主義が敵、というのでは、お馴染みの文明の衝突的二項対立の裏返しになってしまい、面白くない。プロローグでのモンゴルの扱われ方や、ラグルが香港に拠点を置いていることからすると、日本や中国も含めた東洋人(=非一神教徒)が敵、となるか。それではちょっと悲しい。 第二に、99の属性は確かに盤石な基盤だが、それにのっとってキャラを99かき分けるというのは、至難の業だろう。確かに、そんなに主人公が出てきたら読者は混乱する。しかし、水滸伝では「ハンコ作りの名人」みたいなどうでもよさげな能力の持ち主が、108人の英雄豪傑の1人とカウントされていたりする。本作でも、暗算が得意で飲み会の時に重宝する「ハスィーブ(正しく計算する者)」みたいなキャラで埋め合わせをしても良いだろう。「ラフマーン」と「ラヒーム」を双子の兄弟にするとか。 第三はやっぱり、宗教的権威筋からの横やりが入らないことを祈るばかりだ。 ちなみに上記記事の「イスラーム圏初」という表現も、やや正確さを欠く。このブログで以前取り上げたように、エジプトではすでにアメコミ風漫画が登場している。ただし、それらがその後騒がれていないところを見ると、どうやら定着しなかったのだろう。 ともあれ興味ある方は、上記のオンラインショップで無料版を手に入れられたい。本作の壮大なるプロローグと、ジャッバールが登場する「The Origins」の巻が手に入る。また、これからどんなキャラが登場するのか楽しみでならないという方は、ここで神の99の名前をチェックしておきたい。
エジプト人は本を読んでいるか? [読書]
「ヤコービエン・ビルディング」の原作者アラー・アル・アスワーニーが、「エジプト人が本を読まなくなったって!?僕の本はこんなに売れてるじゃないか!」と言ったとか言わないとか(出典al-Quds al-Arabiうろ覚え)。
とは言え、現代エジプト人が読書しなくなったという点では多くの人の意見が一致しているようで、今週のアフラーム・ウィークリーではこんな記事が。
「エジプト人は本を読んでいるか?」
そう言えばカイロの街中いたる所に文房具屋というか謎のグッズを売っているファンシーな店があったけど、あれって昔はみんな本屋だったんだろうか?なんてことが気になってきた。
この記事では、つい最近ダウンタウンにオープンした本屋Al-Baladに代表される「カフェ-ブックストア」について紹介している。若者たちがカプチーノなどをすすりながら、本の背表紙を眺め、あわよくばご購入頂くという商法。すでにザマーレクの書店Diwanではそんなサービスを提供していたが、どうやら同じ経営者らしい。日本でもジュンク堂などが同種のサービスで有名だが、きっとアメリカなどで発明された商法が、世界各国で流行っているのだろう。
しかし、エジプトの場合は老舗書店の常連客になると、店員と長~い挨拶を交わした後、まあまあと椅子を勧められて知らないうちにシャーイが出てきたりする。これってジュンク堂の元祖?と言う気もしないでもないが、しかしこの記事のAl-Baladのお洒落な雰囲気とはほど遠い。エジプトでも、従来の店員と客との濃密なスキンシップを「ウザイ」と感じる人たちが増えているのかも知れない。
さて記事によれば、エジプト出版業界の停滞はひとえに教育の劣化のたまものであり、そしてそれはサダト時代の開放政策に起因するものらしい。具体的に識字率がどう変化したとか、出版部数がどう変わったという数字は示されていないのだが、このことはすでにソースを示して説明するまでもない常識と見なされているのだろうか。
ともあれ、現在カイロにいらっしゃる方は是非ともAl-Baladに行って、ご感想をお聞かせ下さい。アメ大Cilantroの二階だそうです。
とは言え、現代エジプト人が読書しなくなったという点では多くの人の意見が一致しているようで、今週のアフラーム・ウィークリーではこんな記事が。
「エジプト人は本を読んでいるか?」
カイロの多くの本屋で書棚がホコリをかぶったままな状態を見るに付け、あるいはここ十年ほどでいくつかの書店が文房具屋に変わっている現状を見るに付け、エジプトの書籍市場は景気がいいようには見えない。
そう言えばカイロの街中いたる所に文房具屋というか謎のグッズを売っているファンシーな店があったけど、あれって昔はみんな本屋だったんだろうか?なんてことが気になってきた。
この記事では、つい最近ダウンタウンにオープンした本屋Al-Baladに代表される「カフェ-ブックストア」について紹介している。若者たちがカプチーノなどをすすりながら、本の背表紙を眺め、あわよくばご購入頂くという商法。すでにザマーレクの書店Diwanではそんなサービスを提供していたが、どうやら同じ経営者らしい。日本でもジュンク堂などが同種のサービスで有名だが、きっとアメリカなどで発明された商法が、世界各国で流行っているのだろう。
しかし、エジプトの場合は老舗書店の常連客になると、店員と長~い挨拶を交わした後、まあまあと椅子を勧められて知らないうちにシャーイが出てきたりする。これってジュンク堂の元祖?と言う気もしないでもないが、しかしこの記事のAl-Baladのお洒落な雰囲気とはほど遠い。エジプトでも、従来の店員と客との濃密なスキンシップを「ウザイ」と感じる人たちが増えているのかも知れない。
さて記事によれば、エジプト出版業界の停滞はひとえに教育の劣化のたまものであり、そしてそれはサダト時代の開放政策に起因するものらしい。具体的に識字率がどう変化したとか、出版部数がどう変わったという数字は示されていないのだが、このことはすでにソースを示して説明するまでもない常識と見なされているのだろうか。
ともあれ、現在カイロにいらっしゃる方は是非ともAl-Baladに行って、ご感想をお聞かせ下さい。アメ大Cilantroの二階だそうです。
人種差別主義者は馬鹿だわ。 [読書]
--パパ、もし人種差別主義者が恐がっている人だとすると、外国人を嫌う政党の党首[国民戦線の党首ル・ペン]は、いつも外国人を恐がっているはずでしょ。でも、あの人がTVに出るたびに、恐いのは私の方よ。ジャーナリストを怒鳴りつけたり、脅したり、机を叩いたりするわ。
そう。でも、メリエムが話しているその党首は、攻撃的な性格で知られた政治家だ。彼の人種差別主義は、暴力的な仕方で示されるんだ。彼は、よく知らない人たちを恐がらせるために、まちがった主張を伝えている。彼は、人々の恐怖感、ときには現実的な恐怖感をうまく利用する。例えば、移民は、フランス人の仕事を奪ったり、生活保護を受けたり、病院で無料の治療を受けたりするためにフランスに来るんだと言っている。これは本当のことじゃない。移民たちは、多くの場合フランス人がやろうとしない仕事をしている。彼らは税金を払い、社会保険の保険金を払っているから、病気になったときには治療を受ける権利がある。もし明日、不幸にもフランスの移民が全員強制退去させられたとすると、この国の経済は崩壊するだろう。(pp.18-20)
--それは、ルペンに投票する人たちみたいなもの?
(中略)でも、たぶんルペンに投票する人すべてが人種差別主義者ではない・・・不思議なんだが・・・さもないとフランスには400万人以上の人種差別主義者がいることになってしまう!多いだろう!彼らはだまされているんだ。さもなければ現実を見たくないんだ。ルペンに投票しておきながら不安を感じたと言っている人もいる。でも彼らは手段をまちがっている。(pp.52-53)
 タハール・ベン・ジェルーン著『娘に語る人種差別』
タハール・ベン・ジェルーン著『娘に語る人種差別』これ以上言いたいことはありません。ベン・ジェルーンの言うとおり!連れ合いが言うには、フランス人はルペンをせいぜい3番目に選んだに過ぎないけど、日本人(東京都民)はまさしく彼を選んでしまったということ。まあ、大統領に選んだ訳じゃないけど。
あれはひとりの声だったのか [読書]
 ジョン・コルトレーン『至上の愛』の真実
ジョン・コルトレーン『至上の愛』の真実「~の真実」とかいうとなんだか暴露本っぽい雰囲気がして、「今明かされるナイマ夫人との離婚の真相」とか「マッコイとエルヴィンはムチャ険悪説」とか「コルトレーンはUFOに殺された」とかそんな内容を期待してしまうのだが、そうではない。(当たり前だ)
コルトレーンの当時のバンド・メンバーやスタッフ、それから友人、リスナー、家族たちのインタビュー、さらには貴重な録音テープやレコード会社からの支払い明細までを駆使して、『至上の愛』吹き込み前後のコルトレーン周囲の状況を克明に再構成した研究書。
無知な僕にとっては、「コルトレーンがマイルス・バンドを脱退したのは33歳(つまり、今の僕の年齢)」という事実がすでに感動ものなのだが、そんな程度じゃなくてもっと中身のある新事実がてんこもりだ。
たとえば、『至上の愛』第4楽章のコルトレーンのソロは、レコードジャケットに載っている自作の詩のフレーズをそのままサックスで読んだもの、なんてこと、ひょっとしたらコルトレーン・ファンにはもはや常識なのかも知れないけど僕にとっては目から鱗の新発見だった。あと第1楽章での声による「ア・ラヴ・スプリーム...」という詠唱は、実はコルトレーンひとりの声がオーバーダビングされたものだっていうこととか。
個人的な話をすると、大学時代にサークルでサックスを吹いていた僕だけど、コルトレーンはアーティストと言うよりは単なる「教則本」、つまり、彼のソロフレーズを真似てメトロノームに合わせて練習する、というくらいの存在だった。もちろんCDを聴いて「かっこいいなあ」と感じてはいるわけだけど、アーティストとして、あるいは思想家としてどれほど当時の社会にインパクトを与えたのかなんてことは、あんまり考えはしなかった。そもそもジャズ史にもアメリカ現代史にも暗い僕は、『至上の愛』の発売がマルコムX暗殺の年だった、なんていう単純な一致さえも知らなかったわけだ。
こんな巨人の足並みに自分の人生を重ね合わせてしまうのも何とも畏れ多い話だが(それでもついつい考えてしまうのだが)、「何でも教えて君」だったコルトレーンがマイルスに愛想を尽かされて、その後でやたらと面倒見のいいセロニアス・モンクの個人授業をみっちりと受けて、アーティストとして独り立ちする下りなどは、とてもリアルに細かく描かれていて面白かった。それから「黄金のカルテット」のメンバーを徐々に見付けていく部分も、なんだかRPG風でいい。「エルヴィンが仲間に加わった。パーティーのレベルが上がった。冒険を続けますか?」
もう一つ、この本で知った小ネタとしては、コルトレーンの曲の版権を取り仕切るアリス夫人のところにスパイク・リー監督が来て、『至上の愛』という曲名を自分の映画のタイトルに使わせて欲しいと頼みに来たが、見事断られたというエピソード。映画の内容(暴力シーンの有無など)がコルトレーンの思想と合わない、と言う理由だったそうだが、それで『モ・ベター・ブルース』なんてヘンテコな名前の映画だったのか、と納得。
そう言えばあの映画の冒頭で、ウェズリー・スナイプス演じるサックス吹きが延々とソロを取って、バンドリーダーである主人公デンゼル・ワシントンを怒らせるというシーンがあったけど、あれはコルトレーンがマイルス・バンドにいた頃からやたらと長いソロを取っていたコルトレーンを意識したシーンだったのかな、と思った。自分の内にある音楽を形にするためにがむしゃらに吹きまくったコルトレーン(と、それを理解して好きにさせていたマイルス)に対して、ウェズリーの役の方は自分の名前を売るための功利的なロング・ソロ。そんな対比で、商業主義的になってしまった現代ジャズ・シーンをスパイク・リーなりに批判していたのかも知れない。
ともあれ、やっぱりジャズは年取ってから聴くものだよなあ、などと思いながら、久々に『至上の愛』を聴いてみることにする。もちろん、ライナーノーツの「詩」を読みながら。
江湖の笑い者よ [読書]

漂泊のヒーロー―中国武侠小説への道
『大長今』を見終わり、我が家の韓流ブームも一段落、と思ったら、今度は夫婦で中国武侠ドラマに凝ってしまい、妻が図書館で借りてきたこの本をむさぼるように読んでしまいました。
三国志、水滸伝なら日本男子たるもの小中生の頃に読んでしまいますが(漫画で)、そんなメジャーどころの向こう岸には、豊穣な武侠モノの天地が広がっていたんですなあ。それを「江湖」と言い換えても良いでしょう。
ワイヤーアクションばりばりの香港SFX映画は、実は昔からある武侠文学を忠実に映像化したに過ぎなかった、というのには驚かされました。四方田犬彦の「国民的大衆映画」の話なんて、武侠の世界のほんのひとかけらに過ぎなかったんですねえ。『東邪西毒』も『カンフー・ハッスル』ももう一回見直さないと。いやあ、実に楽しそう。中国語ができなくて残念です。
さて、こういう面白い話を聞かされると、アラブ圏ではこれに対応する現象はないのかと、ついつい考えてしまうのがアラビストのサガです。さしあたり、アンタル伝、バイバルス伝などのヒーロー説話が挙げられるでしょう。主人公の周りに任侠無頼の徒が集まるあたり、なんだか「江湖」の香りがします。「崋山派」「崑崙派」と言った武芸の流派は、アラブでは「イスマーイール派」とかになるんでしょうか。
タイの国民的ローカル映画 [読書]
もう一つ、注目のイベント。以前読んだ四方田犬彦の『アジア映画の大衆的想像力』で大きく取り上げられていた、ノンスィー・ニミブット監督の『ナンナーク』という映画が上映されるらしい。
日泰映画人シンポジウム
日泰映画人シンポジウム
イランの少女マルジ [読書]

ペルセポリスI イランの少女マルジ

ペルセポリスII マルジ、故郷に帰る
以前このblogで取り上げた漫画が、ついに日本語訳されて発売されたらしい。「アルプスの少女ハイジ」を思わせる副題だが、まあこれもありだろう。少なくとも、「ちびマルジちゃん」とかでなくってよかった。ちなみに原題は"The story of a childhood"。
NHKテキスト6-7月号 [読書]
NHKラジオのアラビア語講座、皆さん聴いてますか?ていうかテキスト買ってくれた人いますか?(本音)
最近出た6-7月号にもまた僕の文章が載ってますのでご参考まで。
4-5月号の文章はアムル一点張りで、いささか物足りなさを感じた方もいたかもしれません。だから、今回はバランスを取ってアラブ女性歌手のレビューです。語学学習者向けの配慮にも富んだ、バランスの良いレビューになったのではないかと自画自賛しているところですが、どうでしょうか。
さて、次のネタはどうしようか...(ネタ枯渇気味)
NHKラジオアラビア語講座 2005 6・7月―話そう!アラビア語 (2005)
最近出た6-7月号にもまた僕の文章が載ってますのでご参考まで。
4-5月号の文章はアムル一点張りで、いささか物足りなさを感じた方もいたかもしれません。だから、今回はバランスを取ってアラブ女性歌手のレビューです。語学学習者向けの配慮にも富んだ、バランスの良いレビューになったのではないかと自画自賛しているところですが、どうでしょうか。
さて、次のネタはどうしようか...(ネタ枯渇気味)

NHKラジオアラビア語講座 2005 6・7月―話そう!アラビア語 (2005)
ヒーロー見参 [読書]
 「読書」のカテゴリーに漫画のことを書くのは反則なんだけど...
「読書」のカテゴリーに漫画のことを書くのは反則なんだけど...エジプトで出版されて話題のアメコミ風漫画。
Welcome to AK COMICS Inc.:出版社のサイト
Al-Ahram Weekly | Culture | My favourite superhero:新聞のレビュー
現代に生きる最後のファラオZein、中世アラブの戦士Rakan、Zios軍と戦う女闘志Jalila、よく分からないが近未来の女Aya、4人それぞれを主人公とする漫画が流行っているらしい。英語とアラビア語版あり。絵を見たら結構格好いい...と思ったが宣伝用の動画を見たらちょっとダサ感あり。 ディーワーン書店(在ザマーレク@カイロ)などで売っているらしい。欲しい!Y君、これ見てたら立て替えで買っておいてくれない?
今日から兄貴と呼ばせてください [読書]

放送禁止歌
いやあ、この人のきっちりと筋を通す姿勢、すごいです。格好良すぎ。真の漢だ。朝日でこの人が以前書いていたコラムとか、映画の「A」もみたけど、この本もイイ!こんな態度じゃ周りに敵作りまくりだろう、とこっちが心配になるほどだ。
なんかバカっぽい感想しか書けなくてすみません。しかし最近もまたメディアの報道のあり方が問われる重大な事件が明るみに出ているが、この本の森の兄貴とか、NHKの長井さんとか、あくまで筋を通そうとする人がマスメディアの内部にもちゃんといるんだということが分かると、少しほっとさせられる気がいたしまする。いや、NHKの話は決して、この本のような「メディアの自主規制」だけに留めてはいけない問題なのではあるが。
アラブのポップカルチャー [読書]
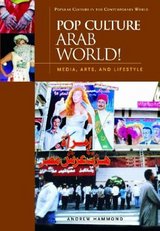 大枚はたきました。
大枚はたきました。Pop Culture Arab World!: Media, Arts, and Lifestyle (Popular Culture)
「アラブ世界のポップカルチャー」と銘打って、ハードカバー、堂々376頁。これは必見本だと思って、発売前からアマゾンで予約!で、それが今日ようやく届いた。見た目はごついが、どうやらシリーズもので、いろんな地域の「ポップカルチャー」をまとめているらしい。"Pop Culture Japan"なんていうのもある。その辺、ガイドブックのLonely PlanetやRough Guideなんかを意識した作りか。 内容は、「概観:現在のアラブ世界」に始まり、「テレビとラジオ」「報道」「映画産業」「音楽とArabpop」「演劇」「民間信仰」「ベリーダンス」「消費」「スポーツ」「アラビア語」と、網羅的。これだけのことをたった一人の人物が書いてしまっているというからすごい。著者はロイターのコメンテーターを務めた人らしい。1970年生まれ! さて問題は中身だ。これからゆっくりとみていきたいが、ざっと眺めてみると、ビンラーディンや捕まったサッダームの顔写真が載っているかと思うと、音楽コーナーにはナンシーやルビーも取り上げられている様子。早!かなり最新の情報に目配りされている。これは楽しみである。
地中海のモザイク [読書]

Mediterranean Mosaic: Popular Music and Global Sounds (Perspectives on Global Pop)
ずっと前に『ミュージックマガジン』誌で、北中さんが紹介していた本。2003年出版。12本の論文のアンソロジーだがうち4本はアラブ圏のポップスに関する論考。アラブ関連は以下の通り
3. Antonio Naldassarre, Moroccan World Beat through the Media 4. Gabriele Marranci, Pop-Rai: from a "Local" Tradition to Globalization 5. Ruth Davis, "New Sounds, Old Tunes": Tunisian Media Stars Reinterpret the Ma`luf 6. Michael Frishkopf, Some Meanings of the Spanish Tinge in Contemporary Egyptian Musicこの第六章を書いている人、かなりのアムル・カセットを所有している模様。いや趣味ではなくて学術的考察の対照として。 そのほかスペイン、トルコ、イスラエル、イタリア、ギリシアに関するものもあり。
マルジャーンについて [読書]
『ペルセポリス』の著者サトラピーについての紹介文。しかしすごい名前だなサトラピーって。
Marjane Satrapi(英語)
Marjane Satrapi: La vie sous le r馮ime des moullas (仏語)
Marjane Satrapi(英語)
Marjane Satrapi: La vie sous le r馮ime des moullas (仏語)
イランのちびまる子ちゃん [読書]
とどこかのサイトに紹介されていた「ペルセポリス」という本の、続編。

Persepolis 2: The Story of a Return第一巻については12/28付けブログに書いたとおりで、年内に読み終えたのだが、下のブログではなぜか画像が表示されていないので、今度は第二巻の方を紹介しておく。これなら多分画像も写っているはず。
著者は1969年生まれ。10歳の時にテヘランに住んでいて、イラン革命を体験している。 イラン革命、イコール「イスラム革命」みたいに捉えられがちだが、少なくとも当初はイスラーム的な方向性を持っていたわけではなくって、著者の叔父のような社会主義者なども荷担していたということが、よく描かれている。著者の両親もかなりのマルキシストで、幼い娘に「まんが唯物論」みたいなものを与えたりしているのが面白い。 そんな環境に育った著者だが、幼い頃は想像の中の「神様」と会話したりする少女だった。で、その「神様」というのが漫画で描かれているのだが、イスラム教の神様なので、ターバンを巻いていたりするのかと思いきや、僕などが思い浮かべるような、杖をついた白髪の老人の神様像なのだ(七福神のようなのじゃなくって)。このイメージってどこから来ているんだろう?僕の場合は映画の「天地創造」なんかに出てくるのがその原型だと思うけど。いやそもそもイスラム世界の神様というのはどういう姿で描かれるんだろうか?エジプトなどでは神様が漫画に書かれるということはまずあり得ないが、イランでは(革命前は)よく描かれていたのだろうか?...ともかくそんな小さなところからも、当時のイラン社会を身近に感じさせてくれるような道具立てがそろっている。 また、革命後のイランはイラクとの戦争に突入するが、そうすると著者は、マルキシストの父親ともども、愛国一家に変貌する。「バグダードに空爆すればいいのに」などと居間でテレビを見ながら話し合ったりするのだ。著者は学校の課題で、「アラブ大征服とこの戦争」というような作文を書いている。もちろんそんな変貌ぶりも、この著者独特のシニカルな語り口によって、良い具合にぼかされて滑稽な感じに描かれている。ただし前書きの文章はやや「愛国的」な感じが鼻につくかな個人的には。 下にも描いたとおり、この物語は著者の成長物語でもあって(というか成長物語の方がメインで)、白髪の神様から自立し、最後には両親からも離れて独り立ちする、という風に描かれている。 表題の「ちびまる子」ちゃんやさくらももこの著作は実は僕は全然読んだことがないのだが、どうも作者と同年代の方々の郷愁を誘うようなものらしい。僕にとっては、こっちのイランのちびまる子ちゃんの方が、世代も近くて共感できるものが多い気がする。ってすごく遠い国の話ではあるので、一口に同世代とまとめるのはやや強引なのだが。 というわけでようやく届いた第二巻の方も、これから読んでみるつもり。

Persepolis 2: The Story of a Return第一巻については12/28付けブログに書いたとおりで、年内に読み終えたのだが、下のブログではなぜか画像が表示されていないので、今度は第二巻の方を紹介しておく。これなら多分画像も写っているはず。
著者は1969年生まれ。10歳の時にテヘランに住んでいて、イラン革命を体験している。 イラン革命、イコール「イスラム革命」みたいに捉えられがちだが、少なくとも当初はイスラーム的な方向性を持っていたわけではなくって、著者の叔父のような社会主義者なども荷担していたということが、よく描かれている。著者の両親もかなりのマルキシストで、幼い娘に「まんが唯物論」みたいなものを与えたりしているのが面白い。 そんな環境に育った著者だが、幼い頃は想像の中の「神様」と会話したりする少女だった。で、その「神様」というのが漫画で描かれているのだが、イスラム教の神様なので、ターバンを巻いていたりするのかと思いきや、僕などが思い浮かべるような、杖をついた白髪の老人の神様像なのだ(七福神のようなのじゃなくって)。このイメージってどこから来ているんだろう?僕の場合は映画の「天地創造」なんかに出てくるのがその原型だと思うけど。いやそもそもイスラム世界の神様というのはどういう姿で描かれるんだろうか?エジプトなどでは神様が漫画に書かれるということはまずあり得ないが、イランでは(革命前は)よく描かれていたのだろうか?...ともかくそんな小さなところからも、当時のイラン社会を身近に感じさせてくれるような道具立てがそろっている。 また、革命後のイランはイラクとの戦争に突入するが、そうすると著者は、マルキシストの父親ともども、愛国一家に変貌する。「バグダードに空爆すればいいのに」などと居間でテレビを見ながら話し合ったりするのだ。著者は学校の課題で、「アラブ大征服とこの戦争」というような作文を書いている。もちろんそんな変貌ぶりも、この著者独特のシニカルな語り口によって、良い具合にぼかされて滑稽な感じに描かれている。ただし前書きの文章はやや「愛国的」な感じが鼻につくかな個人的には。 下にも描いたとおり、この物語は著者の成長物語でもあって(というか成長物語の方がメインで)、白髪の神様から自立し、最後には両親からも離れて独り立ちする、という風に描かれている。 表題の「ちびまる子」ちゃんやさくらももこの著作は実は僕は全然読んだことがないのだが、どうも作者と同年代の方々の郷愁を誘うようなものらしい。僕にとっては、こっちのイランのちびまる子ちゃんの方が、世代も近くて共感できるものが多い気がする。ってすごく遠い国の話ではあるので、一口に同世代とまとめるのはやや強引なのだが。 というわけでようやく届いた第二巻の方も、これから読んでみるつもり。
漫画だけど [読書]

Persepolis: The Story of a Childhood
妻が買った本を勝手に読んでいるのだが。
イラン革命の頃に少女時代を過ごしたマルジャン・サトラピーという漫画家の自伝的作品。子供の目を通したイラン革命と言う感じで物語が進むが、同時に自分の人間的成長過程も描かれていて面白い。
絵がかわいいんだけどすごくシリアスな状況も淡々と描かれている。ようやく半分ほど読んだところだけど、早くも続編が読みたくなり、妻に早く買うようせっついている。
pop culture arab world! [読書]
某書店の新着カタログで発見。

Pop Culture Arab World: Media, Arts, and Lifestyle (Popular Culture)
やや詳しい内容はこれ。
ABC-CLIO

Pop Culture Arab World: Media, Arts, and Lifestyle (Popular Culture)
やや詳しい内容はこれ。
ABC-CLIO
アラベスクってなんだ [読書]

音楽のアラベスク―ウンム・クルスームの歌のかたち
タイトルの「アラベスク」って何のこと?と思っていたのだが、この「アラベスク」こそが本書第三章で、ウンム・クルスームの代表曲三つを分析する際の、重要なキー概念となるのだった。本書は三章構成。 第一章はアラブ・イスラーム音楽の歴史概観。アッバース朝や後ウマイヤ朝でのアラブ音楽の隆盛などもまとめられている。しかし何を参照したのかあまり言及されていないのが残念。 第二章はウンム・クルスームの生涯史。詳しい記述があるが、これもソースが記されず。 メインとなる第三章は、「アラベスク」概念を用いた筆者独自の分析で、本書の核心部分。ここで言う「アラベスク」とは、例の唐草模様のこと。筆者はこの模様こそが、アラブ人、ひいては「イスラームのもつ思考特性とほぼ一致する」と看破し、ウンム・クルスームの楽曲の中から「アラベスク様式」なるものを抽出するのである。 楽曲の中の「アラベスク様式」というのは、唯一性、抽象性、反復性などなどの特徴を指しており、それは唐草模様の特徴と共通しているという。それがインターアートというものだそうだ。 筆者の楽曲の分析は、それぞれ、歌詞の原語提示、その和訳、前奏部・間奏部の採譜、マカーム(旋法)抽出、そして、ステージ上でフレーズのどの部分がリフレインされるかと言うところまで至っており、微にいり細をうがっている。しかし、そんな綿密な分析があるだけに、出た結論が、ウンムクルスームの楽曲におけるアラベスク様式の抽出、というのは、何となく合点がいかない。 そもそもアラベスク模様がアラブ・イスラーム文化の本質!というような言い切りには、若干ついて行けないところがある。百歩譲って、このような言い切りに目をつぶるとしても、だからといって「アラブ近代音楽もまた、アラベスクの諸特質に支配されている」というのは、かなり飛躍があると思う。こうなると、歴史性とかアラブの中での地域性とか、そういう議論が入る余地も無くなってしまうのではないか?ドビュッシーと印象派絵画に共通する特徴がある、と言った話とは、違う次元の話だと思う。 とは言え、本書第三章を初めとする微細な分析や、現代アラブ音楽の概説などは、他では得られない貴重な情報。巻末のウンムクルスーム全曲リスト(曲名和訳付き)もかなりの労作。なにしろ、これだけの情報を邦文で読めるというのが嬉しい。アラブ音楽ファンは「買い」ではないだろうか。 わがままを言えば、アラブ歌謡はウンムクルスームをもって完成されてしまったわけではない。当然現代にまで息づいているものであり、その意味で、本書に「アムル・ディアーブ」のアの字も載っていないのは、どうかと思う。ファンだから言っているわけではなくて。
星野千一夜 [読書]

図説 アラビアンナイト
こちらは池袋東武の三省堂にて発見。買いたかったが衝動を押しとどめてしばし検討。この5月にでたという本。カラー図版が多く面白そうだし、この著者なら内容にハズレはないように思う。ちなみに上の本をぱらっとみたら、巻末の文献リストにこんな本が上がっていた。欲しい。

カイロの邸宅―アラビアンナイトの世界
ウンム・クルスーム研究 [読書]

音楽のアラベスク―ウンム・クルスームの歌のかたち
池袋のHMVを物色中に発見、衝動買い。というか買わずにどうする!という感じ。
中身はまだちゃんと読んでないが、著者は頻繁に「フィールドワーク」とやらを行ってエジプトを訪れているようだし、アラビア語の著作もいくつか文献リストに挙げられている。もちろん、ヴァージニア・ダニエルスンの英文研究書や、最近ネット通販で手に入るウンムクルスームのDVDなども参照してる。いずれにせよ、邦文ではこのようにアラブ歌謡をフィーチャーした単著は類書がない。
イスラーム主義 [読書]
イスラーム主義とは何か
著者自身の留学・在外研究遍歴と重ね合わせる形で、サウジ→スーダン→エジプトのイスラーム主義運動の歴史を概説するという手法、人類学者として学者の「主観」にこだわり続けた著者ならではのものがある。評価したい。
「イスラーム主義」の定義を、「近代」を経験したムスリムたちによる政治運動に限定し、「近代」以前の運動とは区別している点も重要。この著者の定義に従えば、ターリバーンはその「近代性」の希薄さゆえに、「イスラーム主義」運動とは呼ぶべきでない、ということになる(p.212)が、果たしてそうか?このグローバル化の時代に「近代性」が欠如した政治運動などありえるのだろうか、という疑問を抱く。 バンナーによるアフワでの宣教活動についてはp.108。
エジPOP研究 [読書]
非西欧世界のポピュラー音楽
原書は学術書らしいが、中村とうよう氏の翻訳のせいでかなり読みやすくなっている。アラビア語のカタカナ表記がハチャメチャだが(原著者は正確に転写しているのに)、まあしかたないだろう。アラブ中東の項目だけ目を通したが、1989年出版の本なのに、最新事情とえらく違っていて、エジPOPのここ近年の発展ぶりがしのばれよう。



